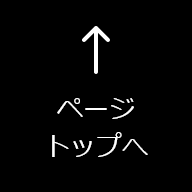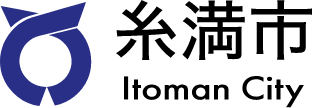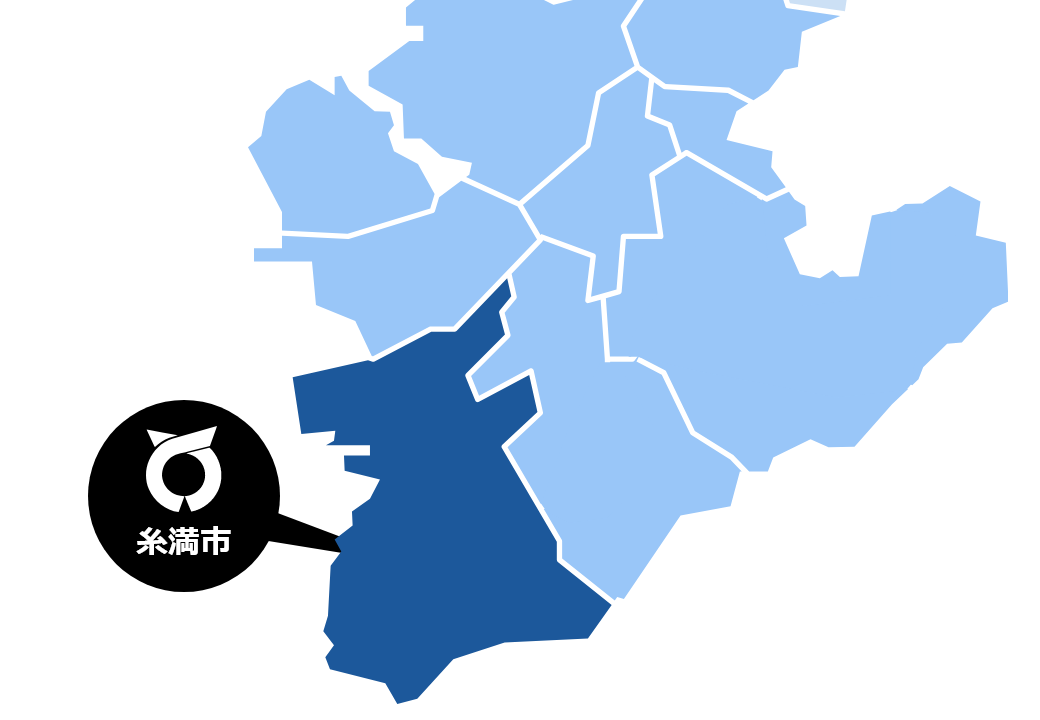本文
国民年金の給付について
目次
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
・特別障害給付金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、年金保険料を納めた期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上ある場合に受けられ、65歳の誕生日の前日より請求できます。希望により繰上げ請求(60歳~)や繰下げ請求(66歳~75歳)することができます。
詳しくは老齢年金ガイド<外部リンク>をご確認ください。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間と免除期間などを併せた10年以上の資格期間が必要です。
老齢基礎年金の受給資格
| 国民年金保険料納付期間+免除期間+厚生年金・共済組合等加入期間+カラ期間≧10年(120)月 | |||||||||
年金額
令和7年度年金額(満額) 年額831,700円(月額69,308円)
※ただし、これは20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額で、未納や免除、学生の納付特例期間がある場合は、期間に応じて減額されます。原則65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から64歳(繰上げ受給)、もしくは66歳以降(繰下げ受給)に受けることもできます。その場合、年金額が減額(繰上げ受給の場合)、増額(繰下げ受給の場合)されます。
請求のお手続き
・本人が国民年金第1号のみ加入していたとき:市区町村国民年金窓口 または年金事務所
・本人が国民年金第3号・厚生年金・共済組合・船員保険等の加入期間があるとき:年金事務所
障害基礎年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができます。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
詳しくは障害年金ガイド<外部リンク>をご確認ください。
障害基礎年金の受給要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること ※初診日とは障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2.初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること(次のいずれかに該当していること)
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3.障害の状態が障害認定日または20歳に到達したときに障害等級表の定める1級または2級に該当していること
障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
詳しくは障害認定日について<外部リンク>をご確認ください。
年金額
1級 1,039,625円/年額 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,036,625円/年額
2級 831,700円/年額 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円/年額
請求のお手続き
・国民年金加入期間または20歳前に初診日がある方など:市町村国民年金窓口または年金事務所
※相談には時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
(請求に必要な書類だけお渡しすることはできません。)
・厚生年金加入期間中に初診日がある方:年金事務所
遺族基礎年金
国民年金に加入している方(保険料の納付要件あり)、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
詳しくは遺族年金ガイド<外部リンク>をご確認ください。
遺族基礎年金の受給要件
下記の1から4のいずれかに該当していること
1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方
が死亡したとき
3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※1、2の場合、納付要件があります
・20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて
3分の2以上あること
・死亡日が令和18年3月末日までの場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料
の未納がないこと
※3、4については、保険料納付済期間、保険料免除期間およびカラ期間をあわせて25年以上
ある方に限ります。
遺族基礎年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます
・子
・子のある配偶者
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
年金額
・子のある配偶者が受け取るとき
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 | ||||||
| 1人のとき | 年額831,700円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方 年額829,300円 |
年額239,300円 |
年額1,071,000円 |
||||||
| 2人のとき | 年額831,700円 ※昭和31年4月1日以前生まれの方 年額829,300円 |
年額478,600円 | 年額1,310,300円 | ||||||
・子が受け取るとき
| 子の人数 | 基本額 | 子の加算額 | 合計 | ||||||
| 1人のとき | 年額831,700円 | ー |
年額831,700円 |
||||||
| 2人のとき | 年額831,700円 | 年額239,300円 |
年額1,071,000円 |
||||||
※子が3人以上のときは1人につき年額79,800円が加算されます。
請求のお手続き
・市町村国民年金窓口または年金事務所(請求に必要な書類については個々によって異なるため窓口へお問い合わせください)
※遺族厚生年金と合わせて請求される方は年金事務所へお問い合わせください。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受けることができます。
詳しくは寡婦年金について(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
《注意事項》
・亡くなった夫が「老齢基礎年金」または「障害基礎年金」を受け取ったことがある場合
は,請求できません。
・妻が繰り上げ受給の「老齢基礎年金」を受け取っている場合も請求ができません。
・妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
・寡婦年金と死亡一時金の両方を受取ることができる場合は、どちらか一方を選択して
受取ることになります。
年金額
| 年額 |
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額×4分の3 |
|||||||
請求のお手続き
市町村国民年金窓口になります。(必要な書類については個々によって異なりますので、市民課年金係へご相談ください)
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済み期間が36月(3年)以上あるある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
詳しくは死亡一時金について(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
≪注意事項≫ ・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
請求のお手続き
市町村国民年金窓口になります。(必要な書類については個々によって異なりますので、市民課年金係へご相談ください)
特別障害給付金
平成3年3月以前に学生のため国民年金任意加入対象だった方、または昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者のため国民年金任意加入対象だった方で、任意加入していなかった期間に初診日があり、障害の程度が障害基礎年金の1級または2級に該当する方に支給されます。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html<外部リンク>