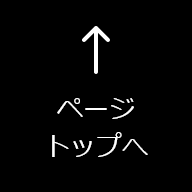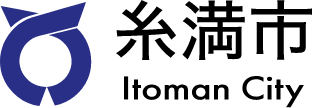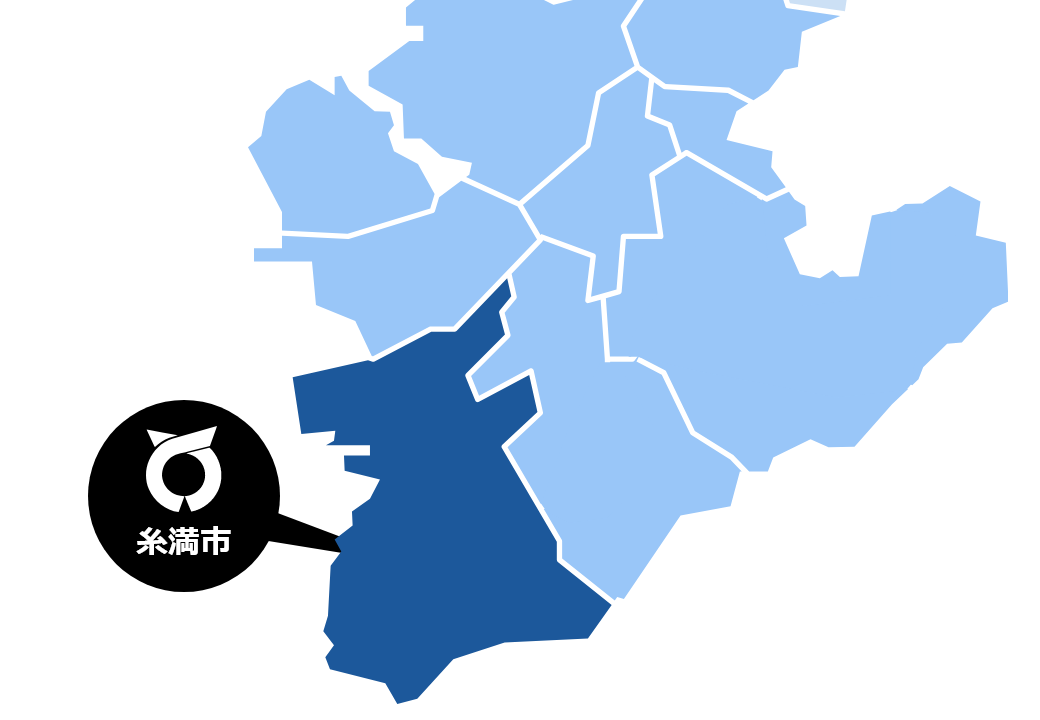本文
介護サービスの利用方法
介護サービスの利用方法
要介護認定の申請からサービス利用までの流れ
サービスを利用したいときは、糸満市から「要介護認定」を受ける必要があります。認定を受けるための申請からサービスの利用までの流れは次のようになっています。
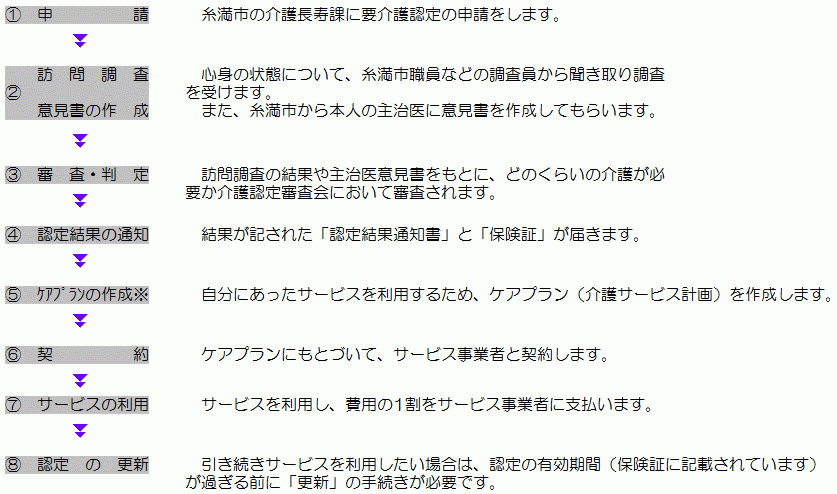
※ケアプランの作成
認定を受けた後に、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者と面接します。ケアマネジャーは利用者の状況を把握し、利用者や家族、サービス事業者と話し合い、利用者にあったケアプランを作成します。
認定申請の手続きに必要なもの
- 申請書(介護長寿課の窓口にあります)
- 介護保険の保険証(40〜64歳の第2号被保険者は、医療保険の保険証)
認定申請を代行してくれる機関
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業者
- 介護保険施設等
要介護状態の区分
要支援状態または要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。
非該当(自立)と判定された場合には、介護保険サービスは利用できませんので、市の保健・福祉サービスなどを利用していただくことになります。
介護長寿課窓口や地域相談センター等にてご相談下さい。
| 要介護度 | 心身の状態像 |
|---|---|
| 自立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
| 要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作をおこなう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 |
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |