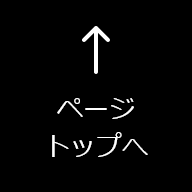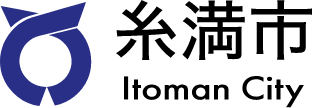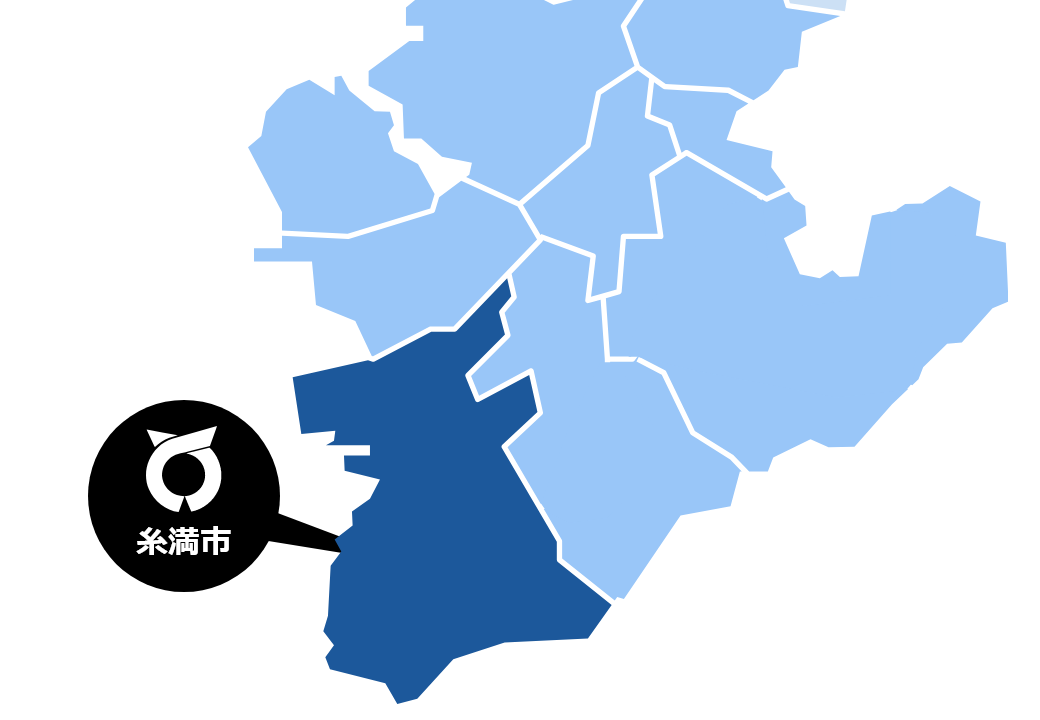本文
No.24 浮きの取り付け作業

801-114-1-18-394
1958(昭和33)年。字糸満の町端区にある浜に向かってのびるカンジャージョーグヮーと呼ばれる細い路地。
冬の仕事着であるモーフギン(毛布衣)を着た男たちが、アンブシ(建干網)用の網に浮きの取り付け作業をしている。
アンブシとは遠浅の海域で定置網を張って行う漁法のこと。
主にエーグヮー、アマユー、チン、カタカシなどが獲れた。
手前の若者は屋号「新出浜山戸拝見」の三男の上原庸孝さん。
上原さんが口にくわえているのはアグイといい、網を繕ったりするのに利用する。
浮きは杉板製の14、5センチほどの細長い棒状のもので、全て自分たちの手作り。
定規で浮きと浮きの間を等間隔に測りながら、アグイを使って浮きを網に固定する。
1枚の網を仕上げるのに40分ほどかかったという。
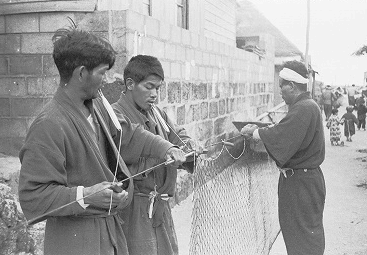
801-114-1-18-388
(写真 東風平朝正氏)