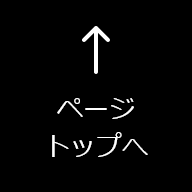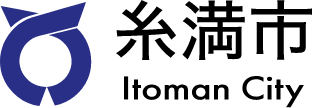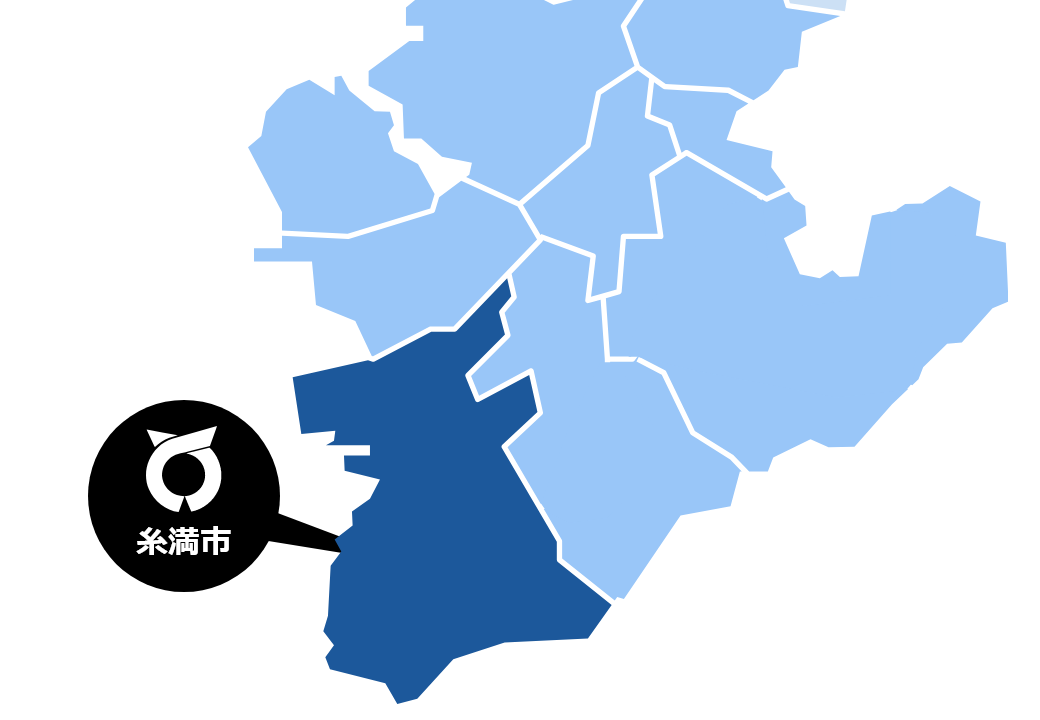本文
教えて!市民税・県民税(住民税)について
市民税・県民税(住民税)とは
▶市民税と県民税(住民税)
▶個人の住民税と法人の住民税
▶住民税の内訳
個人住民税のあらまし
下記の事項については、令和5年度税制改正に基づいた記載になっておりますので、対象年度が異なる場合は数値の変動があることを予めご了承ください。
▶住民税を納める人(納税義務者)
| 糸満市に住所がある人 |
糸満市に住所はないが、事務所、事業所 または家屋敷のある方 |
|
|---|---|---|
| 均 等 割 | 〇 | 〇 |
| 所 得 割 | 〇 | ー |
※糸満市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
▶住民税が課税されない人
〇均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の年収に直すと204万4,000円未満)であった人
| 均等割 | 扶養無 |
給与収入 93万円以下 |
合計所得 38万円以下 |
| 扶養有 |
28万円×家族数+26万8千円 以下 ※家族数は本人と被扶養者(年少も含む)の合計 |
||
| 扶養1人 所得 82万8千円 以下 | |||
| 扶養2人 所得110万8千円 以下 | |||
| 扶養3人 所得138万8千円 以下 | |||
| 扶養4人 所得166万8千円 以下 | |||
| 所得割 | 扶養無 |
給与収入 100万円以下 |
合計所得 45万円以下 |
| 扶養有 |
35万円×家族数+42万 以下 ※家族数は本人と被扶養者(年少含む)の合計 |
||
| 扶養1名 所得112万円 以下 | |||
| 扶養2名 所得147万円 以下 | |||
| 扶養3名 所得182万円 以下 | |||
| 扶養4名 所得217万円 以下 | |||
▶住民税の課税について
均 等 割
▶均等割の税額
個人の住民税の均等割は、県民税年額1,000円(標準税額)、市民税年額3,000円(標準税額)と定められています。
※標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
※糸満市に住所がなくても、糸満市内に事務所・事業所または家屋敷がある場合でも均等割の課税がされる場合があります。
所 得 割
▶所得割の計算方法
|
(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額 = 所得割額
↑_課税所得金額_↑ |
住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
(ア)所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除の額はそれぞれ48万円、38万円ですが、
住民税の控除額はそれぞれ43万円、33万円です。
(イ)平成27年分から税率は、所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階になっています
が、住民税は所得の多寡にかかわらず、比例税率とされ糸満市の場合(標準税率)、県民税は一
律4%、市民税は一律6%です。
所 得 金 額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば令和5年度の住民税では、令和4年中の所得金額が基準となります。
| 所 得 の 種 類 | 所得金額の計算方法 | |
| 給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額ー給与所得控除額ー特定支出控除額=給与所得の金額 |
| 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
| 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額ー必要経費=事業所得の金額 |
| 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額ー必要経費=不動産所得の金額 |
| 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額ー資産の所得価額などの経費ー特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 雑所得 |
公的年金、自治連絡員報酬、 |
次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額 (1) 公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額 (2) (1)を除く雑所得の収入金額ー必要経費 |
| 一時所得 | 生命保険契約の返戻金、自衛隊の二回目の退職金など | 収入金額ー必要経費ー特別控除額=一時所得の金額 |
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額ー必要経費ー特別控除額=山林所得の金額 |
所 得 控 除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
| 種 類 | 控 除 額 |
|---|---|
| 基礎控除 |
納税義務者の前年の合計所得金額 |
| 雑損控除 | 次のいずれか高い金額 (1)(損失金額ー保険等により補うされた額)-(総所得金額等×1/10) (2)(災害関連支出の金額ー保険金等により補うされた額)-5万円 |
| 医療費控除 | (1)(医療費の実質負担額ー保険金等により補てんされる額)ー総所得額×5/100 or 10万円のいずれか低い額(限度額200万円) (2)(特定一般用医療薬品等購入額ー保険金等で補てんされる額)-1万2千円(限度額8万8千円) (1)または(2)のいずれか |
| 社会保険料控除等 | 支払金額 |
| 生命保険料控除 |
(1)旧契約(H23.12.31以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料または個人年金保険料を支払った場合(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円) |
| 地震保険料控除 |
地震保険・・・支払地震保険料の2分の1(限度額25,000円) |
| 障がい者 控除 |
・障碍がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び親族1人につき・・26万円 ただし、その障がい者が特別障がい者である場合・・30万円 ・控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障がい者である場合・・53万円 |
| 寡婦控除 | 納税義務者が寡婦の場合・・・・26万円 |
| ひとり親 控除 |
納税義務者がひとり親の場合・・30万円 |
| 勤労学生 控除 |
納税義務者が勤労学生の場合・・26万円 |
| 扶養控除 |
・控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。) |
| 種 類 | 控 除 額 |
|---|---|
| 配偶者控除 |
生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下で事業専従者に該当しない者に限る。)を有する納税義務者の前年の合計所得金額 ア 900万円以下の場合 ・・・・・・・・33万円(38万円) |
| 配偶者 特別控除 |
生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が133万円以下で事業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
(2) 納税義務者の前年の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 (3) 納税義務者の前年の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
|
税 額 控 除
| 人的控除額の差 | (参考)人的控除額 | |||
| 住民税 | 所得税 | |||
| 障がい者控除 | 普通 | 1万円 | 26万円 | 27万円 |
| 特別 | 10万円 | 30万円 | 40万円 | |
| 同居特別障がい者 | 22万円 | 53万円 | 75万円 | |
| 寡婦控除 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |
| ひとり親控除 | 母である者 | 5万円 | - | - |
| 父である者 | 1万円 | - | - | |
| 勤労学生控除 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |
| 配偶者控除 | 一般 | 5万円 (※2) |
33万円 | 38万円 |
| 老人 | 10万円 (※2) |
38万円 | 48万円 | |
| 配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 |
5万円 (※2) |
33万円 | 38万円 |
| 配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 |
3万円 (※2) |
33万円 | 36万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | 33万円 | 38万円 |
| 特定 | 18万円 | 45万円 | 63万円 | |
| 老人 | 10万円 | 38万円 | 48万円 | |
| 同居老親 | 13万円 | 45万円 | 58万円 | |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下 | 5万円 | 43万円 (※1) |
48万 (※1) |
※1 実際の控除額とは異なる場合がございます。
※2 配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおり。
| 所得割の納税義務者の合計金額 | 人的控除差 | |
| 一般 | 老人 | |
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
3万円 |
| 所得割の納税義務者の合計金額 | 人的控除差 | |
|
配偶者の合計所得金額 |
配偶者の合計所得金額 50万円超55万円未満 |
|
| 900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
配当控除
国内に本店(または主たる事業所)を有する法人から支払を受けた配当等に係る配当所得(外国法人の国内営業所等から受ける一定のものを含む。)があるときは、次の金額を税額から差し引くことができます。
| 課税所得金額 (種類) |
1,000万円 以下の部分 |
1,000万円 超の部分 |
||
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 外貨建等以外の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、(1)から(2)を控除した金額
(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(限度額97,500円)を超える場合には、この金額)に下欄の割合を乗じた金額
ただし、住居年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第第61条の規程の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。)または特例特別特例特殊に該当する場合には「100分の5」を「100分の7」と「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額または平成19年若しくは平成20年の住居年に係る住宅借入金等の金額を有す
る場合には、該当金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・市(区)町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市(区)町村が条例で定める寄附金となります。
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合にはこの30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の都道府県民税は4%、市町村民税は6%に相当する金額
1 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
2 住所地の道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に貢献する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に貢献する寄附金として住所地の道府県または市町村の条例で定めるもの
ただし、1のうち特例控除の対象となる寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
| 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
| 0円以上195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超330万円以下 | 79.79% |
| 330万円超695万円以下 | 69.58% |
| 695万円超900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% |
| 4,000万円超 | 44.055% |
| 0円未満 (課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
| 0円未満 (課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) |
地方税法に定める割合 |