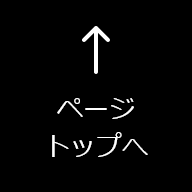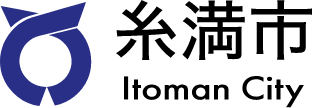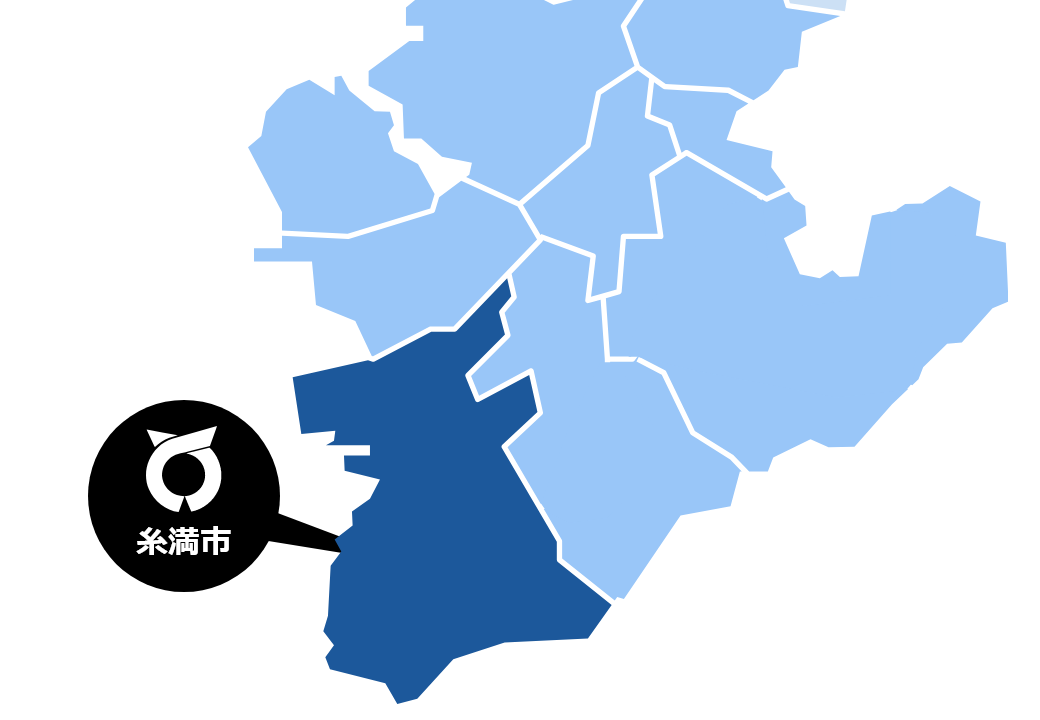本文
国民年金保険料の免除
目次
国民年金保険料免除 納付猶予申請
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な方は糸満市国民年金窓口や年金事務所などで「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。(郵送も可)後日、日本年金機構で審査し承認されると、申請した期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると「障害基礎年金」「遺族基礎年金」等が受けられない場合がありますので、お早めに手続きをしてください。
対象者
【保険料免除申請】 申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれが次のいずれかに該当する方
【保険料納付猶予申請】 申請者本人が50歳未満で申請者本人、申請者の配偶者が次のいずれかに該当する方
1 前年所得が基準額以下の方
| 免除の種類 | 所得基準 | |||||
| 全額免除 納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | |||||
| 4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | |||||
| 半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | |||||
| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | |||||
※地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、お手続きの際にお問い合わせください。
2 失業により保険料を納めることが困難な方
3 生活保護法による生活扶助以外の扶助やその他の援助で、厚生労働省令で定めるものを
受けている方
4 震災・風水害等で被災した方 (詳しくは災害を理由とする免除申請についてをご確認ください)
5 特別障害給付金を受けている方
必要な書類
1 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【雇用保険に加入していた場合】
・雇用被保険者離職票(コピー可)
・雇用保険受給資格者証(コピー可)
・雇用被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)等"
【公務員等場合】
・退職辞令(コピー可)など"
【自営業の場合】
・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し
・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)等
※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年6月分
までです。
3 委任状 (代理人が請求する場合)委任状様式<外部リンク>
学生納付特例申請
学生で国民年金保険料を納めることが困難な方は糸満市役所国民年金窓口や年金事務所などで「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。(郵送も可) 後日、日本年金機構で審査し承認されると、申請した期間の保険料の納付が猶予されます。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると「障害基礎年金」「遺族基礎年金」等が受けられない場合がありますので、お早めに手続きをしてください。
対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在籍する方(夜間、定時制課程や通信課程含む)で前年所得が基準額以下である方
所得の基準
| 所得基準額 | |||||
| 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 |
必要な書類
1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.在籍期間の確認ができる学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
3.退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
(失業をした場合の添付書類についてをご確認くだい)
保険料免除等と年金給付について
老齢基礎年金を受給するときに、保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて年金が減額されて支給されます。保険料の免除や納付猶予(学生納付特例)は、以下のとおり、その期間が年金額に反映されるかに違いがあります。
| 納付 | 全額免除 | 一部免除 | 納付猶予 (学生納付特例) |
未納 | ||||||||||
| 年金を受けるための要件となる受給資格期間に・・・ | 含まれる | 含まれる | ・減額された保険料を納めた→含まれる ・減額された保険料を納めてない→含まれない |
含まれる | 含まれない | |||||||||
| 老齢基礎年金額の計算に・・・ | 含まれる | 含まれる(注) | ・減額された保険料を納めた→含まれる(注) ・減額された保険料を納めてない→含まれない |
含まれない | 含まれない | |||||||||
(注)保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額の割合が以下のとおりになります。 全額免除の場合…2分の1 4分の3免除の場合…8分の5 半額免除の場合…4分の3 4分の1免除の場合…8分の7
免除した保険料の追納制度
保険料の免除、納付猶予(学生納付特例)を受けた期間は老齢基礎年金額が、保険料を納めた場合よりも低額になります。そこで生活にゆとりができたときは10年前まで遡って納めることができる「追納」をおすすめします。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ金額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
ただし、3年目以降の期間を追納するときは、当時の保険料に加算額が付きます。なお、追納を希望するときは古い月から順次納めなければなりませんが、納付猶予(学生納付特例)よりも前に保険料免除期間がある場合はどちらを優先して納めるか本人が選択できます。 詳しくはこちらから→追納制度について日本年金機構ホームページ<外部リンク>