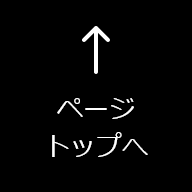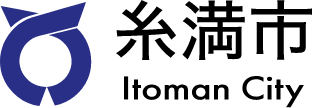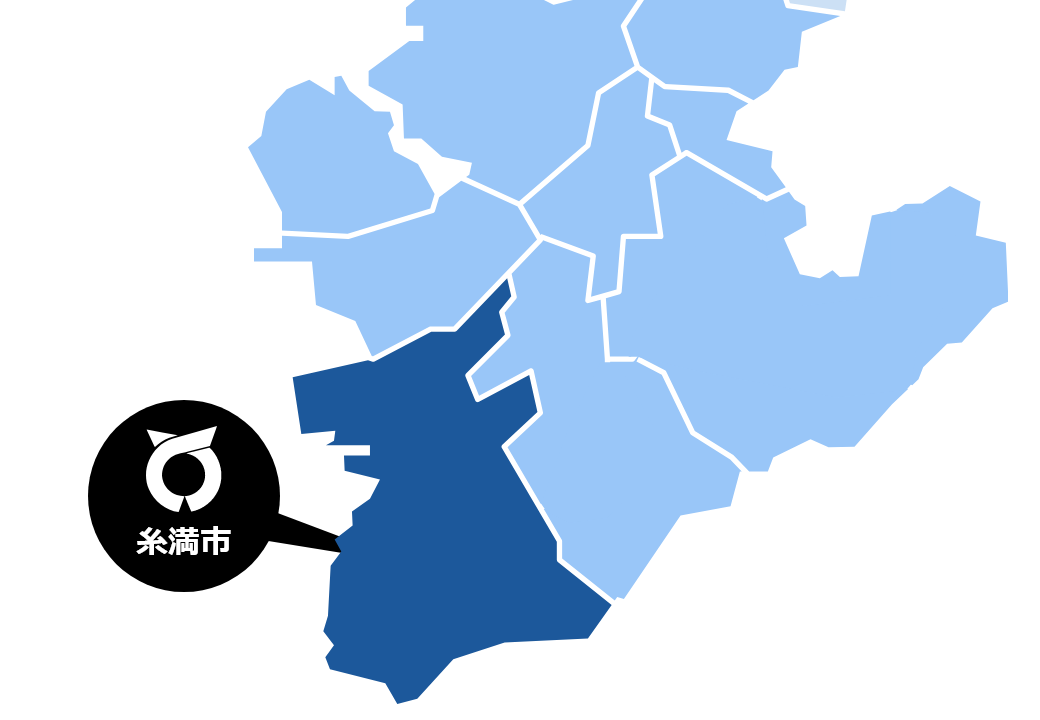本文
令和7年度の国民健康保険税の納税通知書を送付しました
国民健康保険税額の決め方
糸満市の国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分と介護分を項目ごとに計算し、合計して決められます。世帯主の方が納税義務者となります。
項目について
- 所得割額=加入者全員の所得に応じて計算します。
- 資産税割(なし)
- 均等割額=加入者の人数に応じ、赤ちゃんからお年寄りまで1人いくらと計算します。
- 平等割額=一世帯いくらと計算します。
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 8.00% | 27,000円 | 22,000円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援分 | 2.45% | 8,300円 | 6,800円 | 26万円 |
| 介護保険分 | 1.95% | 8,600円 | 4,700円 | 17万円 |
※国民健康保険法施行令の改正により、令和7年度から以下の点が変更となりました。
・医療保険分の限度額が65万円から66万円に引き上げとなりました。
・後期高齢者支援分の限度額が24万円から26万円に引き上げとなりました。
※届出により産前産後の国民健康保険税が免除になります。(原則、世帯主が届け出る必要があります)
・出産する(した)国民健康保険被保険者の保険税のうち、所得割額と均等割額の一定期間分が免除になります。
年齢別にみた国民健康保険税
- 40歳未満の人 国保税=医療分+支援分(介護分の負担はありません)
- 40〜64歳の人 国保税=医療分+支援分+介護分
- 65歳以上の人 国保税=医療分+支援分(介護分は介護保険料として別々に納付)
保険税の軽減制度について
世帯の合計所得が、国の一定基準を下回る世帯については、保険税の均等割額・平等割額が軽減されます。
世帯の加入者数と合計所得に応じた軽減割合は下表のとおりです。
| 区分 |
軽減判定基準額 ※国民健康保険法施行令の改正により、令和7年度から 5割軽減基準額と2割軽減基準額の判定基準所得額が改正されました |
|
|---|---|---|
|
7割軽減 基準額 |
基礎控除 43万円 +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
|
|
5割軽減 基準額 |
基礎控除 43万円 +(30万5千円(※29万5千円から30万5千円に改正)×加入者数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
|
|
2割軽減 基準額 |
基礎控除 43万円 +(56万円(※54万5千円から56万円に改正)×加入者数) +{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
|
《軽減判定基準額算定表》
| 被保険者数 | 給与所得者等数 | 総所得金額等(世帯員(擬主含)の合計所得) | ||
|---|---|---|---|---|
| 7割軽減世帯 | 5割軽減世帯 | 2割軽減世帯 | ||
|
1 |
1 |
430,000円 |
735,000円 | 990,000円 |
| 2 | 1 | 430,000円 | 1,040,000円 | 1,550,000円 |
|
2 |
530,000円 | 1,140,000円 | 1,650,000円 | |
| 3 | 1 | 430,000円 |
1,345,000円 |
2,110,000円 |
| 2 | 530,000円 | 1,445,000円 | 2,210,000円 | |
| 3 | 630,000円 | 1,545,000円 | 2,310,000円 | |
| 4 | 1 | 430,000円 | 1,650,000円 | 2,670,000円 |
| 2 | 530,000円 | 1,750,000円 |
2,770,000円 |
|
| 3 | 630,000円 | 1,850,000円 | 2,870,000円 | |
| 4 | 730,000円 | 1,950,000円 | 2,970,000円 | |
| 5 | 1 | 430,000円 | 1,955,000円 |
3,230,000円 |
| 2 | 530,000円 | 2,055,000円 | 3,330,000円 | |
| 3 | 630,000円 | 2,155,000円 | 3,430,000円 | |
| 4 | 730,000円 | 2,255,000円 | 3,530,000円 | |
| 5 | 830,000円 | 2,355,000円 | 3,630,000円 | |
※ 世帯員に未申告の人がいる世帯は、軽減の対象にはなりません。
※ 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
※ 判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の世帯の加入者数を用います。
※ 4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
※ 加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険制度から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
※ 未就学児の均等割は、軽減適用後の金額からさらに5割軽減されます。
所得(収入)の申告について
国民健康保険税の所得割額は、前年の所得をもとに算定されます。国民健康保険事業の健全な運営を図るため正しい所得申告をお願いします。また、所得に応じた国民健康保険税や給付(高額療養費や入院時食事負担額など)の軽減制度がありますが、未申告の場合は軽減が受けられないことがあります。
国民健康保険税の計算例
モデルケース(1) 2割軽減世帯
夫(42歳)と妻(38歳)、子ども2人(未就学児ではない)の世帯で、前年中の夫の総所得金額が250万円、妻の総所得金額が0円の場合
※所得割対象額=総所得金額-基礎控除額(43万円) 所得対象者毎に算出し合計
・所得割対象額 2,500,000円(夫)-430,000円=2,070,000円
- 所得割額 (医療分207万円×8.00%=165,600円)+(支援分207万円×2.45%=50,700円)+(介護分207万円×1.95%=40,300円)=
計256,600円 (1)
- 均等割額 (医療分27,000円×4人=108,000円)+(支援分8,300円×4人=33,200円)+(介護分8,600円×1人=8,600円)=計149,800円 (2)
- 平等割額 (医療分22,000円)+(支援分6,800円)+(介護分4,700円)=計33,500円 (3)
- 軽減額 (均等割149,800円×20%ほぼ等しい30,000円)+(平等割33,500円×20%=6,700円)=計36,700円 (4)
- 合計 403,200円《((1)256,600円+(2)149,800円+(3)33,500円)-(4)36,700円》
モデルケース(2) 5割軽減世帯
夫(42歳)と妻(38歳)、子ども2人(未就学児ではない)の世帯で、前年中の夫の総所得金額が140万円、妻の総所得金額20万円の場合
※所得割対象額=総所得金額-基礎控除額(43万円) 所得対象者毎に算出し合計
・所得割対象額 1,400,000円(夫)-430,000円=970,000円
・所得割対象額 200,000円(妻)-430,000円=0円
- 所得割額 (医療分97万円×8.00%=77,600円)+(支援分97万円×2.45%=23,700円)+(介護分97万円×1.95%=18,900円)=計120,200円 (1)
- 均等割額 (医療分27,000円×4人=108,000円)+(支援分8,300円×4人=33,200円)+(介護分8,600円×1人=8,600円)=計149,800円 (2)
- 平等割額 (医療分22,000円)+(支援分6,800円)+(介護分4,700円)=計33,500円 (3)
- 軽減額 (均等割149,800円×50%=74,900円)+(平等割33,500円×50%ほぼ等しい16,800円)=計91,700円 (4)
- 合計 211,800円《((1)120,200円+(2)149,800円+(3)33,500円)-(4)91,700円》
モデルケース(3) 7割軽減世帯
夫(42歳)と妻(38歳)、子ども2人(未就学児ではない)の世帯で、前年中の夫の総所得金額が43万円、妻の総所得金額0円の場合
※所得割対象額=総所得金額-基礎控除額(43万円) 所得対象者毎に算出し合計
・所得割対象額 430,000円(夫)-430,000円=0円
- 所得割額 (医療分0万円×8.00%=0円)+(支援分0万円×2.45%=0円)+(介護分0万円×1.95%=0円)=計0円
- 均等割額 (医療分27,000円×4人=108,000円)+(支援分8,300円×4人=33,200円)+(介護分8,600円×1人=8,600円)=計149,800円 (1)
- 平等割額 (医療分22,000円)+(支援分6,800円)+(介護分4,700円)=計33,500円 (2)
- 軽減額 (均等割149,800円×70%ほぼ等しい104,900円)+(平等割33,500円×70%=23,500円)=計128,400円 (3)
- 合計 54,900円《((1)149,800円+(2)33,500円)-(3)128,400円》
モデルケース(4) 軽減非該当世帯
夫(42歳)と妻(38歳)、子ども2人(未就学児ではない)の世帯で、前年中の夫の総所得金額が300万円、妻の所得基準額0円の場合
※所得割対象額=総所得金額-基礎控除額(43万円) 所得対象者毎に算出し合計
・所得割対象額 3,000,000円(夫)-430,000円=2,570,000円
- 所得割額 (医療分257万円×8.00%=205,600円)+(支援分257万円×2.45%=62,900円)+(介護分257万円×1.95%=50,100円)=
計318,600円 (1)
- 均等割額 (医療分27,000円×4人=108,000円)+(支援分8,300円×4人=33,200円)+(介護分8,600円×1人=8,600円)=計149,800円 (2)
- 平等割額 (医療分22,000円)+(支援分6,800円)+(介護分4,700円)=計33,500円 (3)
- 軽減額 0円
- 合計 501,900円《(1)318,600円+(2)149,800円+(3)33,500円》
※税額は100円未満切り捨て、軽減額は100円未満切り上げ
※国民健康保険税は年度単位で決まりますので、年度の途中で加入、脱退したときなどは加入期間分保険税を月割で計算します。
他市町村から転入した場合
糸満市に転入して国民健康保険に加入された方については、国民健康保険税の計算のもととなる所得が不明のため、前住所地に所得の照会を行います。
このため、転入後最初にお送りする国民健康保険税の納税通知書は、均等割額、平等割額のみでお知らせする場合があります。
その後、所得が判明した時点で国民健康保険税を再計算し、保険税に増減が生じた場合は、再度、国民健康保険税決定(更正)通知書をお送りいたします。
国民健康保険税の納付について(普通徴収)
国民健康保険税は4月から翌年3月までの12カ月を前年の所得をもとに算出し、加入月分を納付いただくことになります。糸満市では、基本的に8回の納期が設けられています。
送付される納税通知書で、コンビニや銀行等でお支払いできますが、QRコード読み取りでスマホ決済、クレジット払い、インターネットバンキング等でもお支払いができます。納め忘れの心配のない口座振替も利用できます。
それぞれの納期は以下のようになっています。
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 翌1月末日 | 翌2月末日 |
※月末が土曜日・日曜日・祝日・祭日に当たる場合は、金融機関等の翌営業日が納期限になります。
65〜74歳の特別徴収について
国民健康保険被保険者全員が65〜74歳の人だけの世帯では、原則として国民健康保険税の納付方法が「特別徴収」になります。
「特別徴収」とは、世帯主が受給する年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより、国民健康保険税を納付していただく制度です。
※特別徴収の対象にならない場合は、口座振替等により納付していただく普通徴収になります。
- 特別徴収の対象となる人
- 被保険者全員が65〜74歳であること
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
- 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えないこと
- 特別徴収の方法
年6回の年金受給額から国民健康保険税を差し引きます。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
口座振替に変更することも可能です
国民健康保険税を年金から天引きで納めている人で、口座振替による納付へと変更を希望する方は市役所国民健康保険課窓口で手続きをしてください。
※滞納がある場合などは口座振替に変更できないことがあります。
納められないとき
- 国民健康保険税の期限内納付が難しいときは市役所国民健康保険課窓口で納付計画について相談してください。平日に納付相談が難しい場合は、日曜相談窓口を設けていますのでご利用してください。
【毎月第4日曜日(12月は第3日曜日)の13時から17時まで開設】 - 災害や失業などで国民健康保険税等の納付が難しいときは、減免や医療費の一部負担金の免除の制度や徴収猶予などによる納付相談も行っていますのでお早めにご連絡をお願いします。
国民健康保険税を滞納すると
特別な理由がないのに国民健康保険税を納めないでいると次のような措置がとられることになります。
- 国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)が全額または一部差し止められます。
- 特別療養費の対象となる場合があります。その際は保険の給付が差し止められ、いったん医療費を全額自己負担することになります。
- 納税義務者の資産(土地・建物・預貯金・給与など)を差押することもあります。