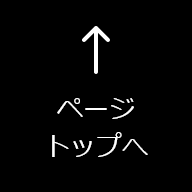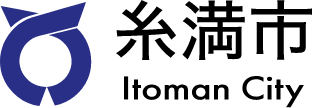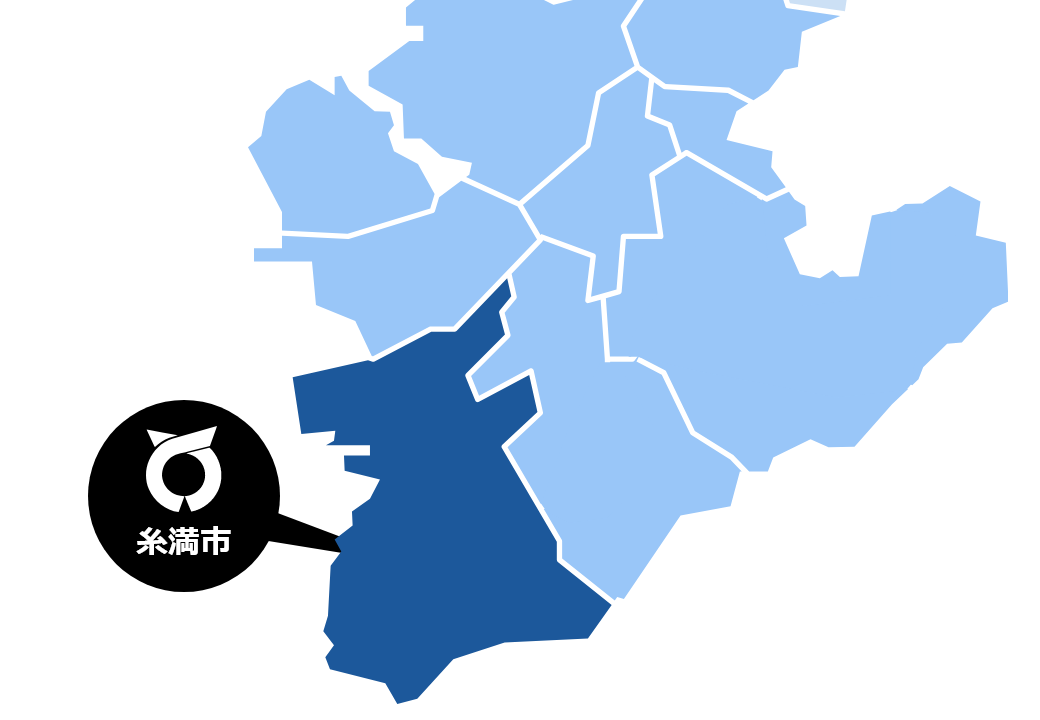本文
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父または母や父または母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
※平成26年12月より、公的年金を受給中の方も、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
受給資格者
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母とも不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月追加)
※前述でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(4月1日生まれは早生まれと同様)または、20歳未満の一定の障害を有する児童をいいます。
手当の額(所得制限あり)
(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 月額 46,690円 |
月額 46,680円~11,010円 (所得に応じて10円きざみの額) |
| 児童2人以上のとき |
上記に2人目以降の児童1人につき 11,030円加算 |
上記に2人目以降の児童1人につき 11,020円~5,520円加算 (所得に応じて10円きざみの額) |
申請者の所得(養育費を含む)及び生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により支給額が決まります。
申請者及び扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。
※令和6年11月分以降の児童扶養手当について、制度改正が行われ、所得限度額および第3子以降の加算額の引き上げられました。詳しくは、下記よりご確認ください。
令和6年11月分(令和7年1月振込分)以降の児童扶養手当の制度改正(拡充)について
手当の支払い
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払時期は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。支払は、各支払月の11日(11日が土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの分が支払われます。
手続きに必要な書類
戸籍謄本・健康保険証・年金手帳・請求者名義の通帳など
※該当事由により添付書類等の提出を求める場合がありますので、申請の前に窓口にご相談ください。
手当を受けている人の手続き
現況届
手当を受けている人は、毎年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年8月に必要書類を添付の上、窓口に提出してください。※7月中にご自宅へ案内文を送付します。
この届けを提出しないと8月分以降の手当てが受けられなくなる可能性や期限を過ぎて提出した場合、手当の支払いが遅れる場合があります。
2年間この届けを提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。
一部支給停止除外届(児童扶養手当法第13条の3による規定)
児童扶養手当制度は、離婚などにより激変する生活を緩和し、ひとり親家庭の自立を促進するという趣旨に改正されたことにより、一定期間手当を受給した人は、手当額の一部が停止になる可能性があります。ただし、一部支給停止適用除外の事由に該当する人は、期限内に一定の手続きを行った上で、その年度の一部支給停止を除外する事ができます。対象者には、通知を送付いたしますので現況届とともに手続きを行ってください。
対象者
下記のいずれかに該当する方は一部支給停止の対象になります。
・手当の支給開始月の初日から起算して5年経過した受給者
・手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過した受給者
※ただし、対象者は児童の父母に限り、養育者は該当しません。また、認定請求日に3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月から起算して5年を経過したときになります。
一部支給停止除外事由
次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。(ただし、所得や世帯状況に変更がある場合はその限りではありません。)
・就業している。
・求職活動等の自立を図るための活動をしている。
・身体上または精神上の障害がある。
・負傷または疾病等により就業することが困難である。
・児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。
様式
児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書 [PDFファイル/135KB]
求職活動支援機関等利用証明書(様式6の1) [PDFファイル/83KB]
受給資格に該当しなくなった場合の手続き
下記のような場合は、資格喪失の手続きが必要になります。該当する場合は、速やかに手続きを行ってください。
・結婚した。または内縁関係、同居など事実上の婚姻状態になった。
・支給事由が遺棄の場合、児童の父(母)親が見つかった。(連絡、仕送等を含む)
・支給事由が障害の場合、父(母)親の障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなった。
・支給事由が拘禁の場合、父(母)親が拘禁解除になった。(仮出所を含む)
・手当を受ける対象となっている児童が、児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた。受給者が児童の面倒をみなくなった。(児童が婚姻した場合、父(母)親に引き取られた場合を含む)
・その他(児童が死亡した、日本国内に住所がなくなった場合など)
※資格喪失後に手当の受け取りがある場合は、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。なお、偽りその他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。
「公的年金等」と「児童扶養手当」の両方受給について
公的年金等(※1) を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。(※2)
(※1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2) 障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
そのため、公的年金等を受給する場合は以下の手続きを児童扶養手当担当窓口にて必ず行ってください。
・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)を持参の上、公的年金給付等受給状況届の提出が必要となります。
● 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、市区町村への手続きが遅れた場合
→ 過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。
詳しくは、児童扶養手当担当までお問い合わせください。