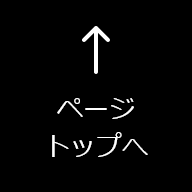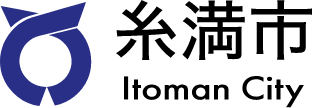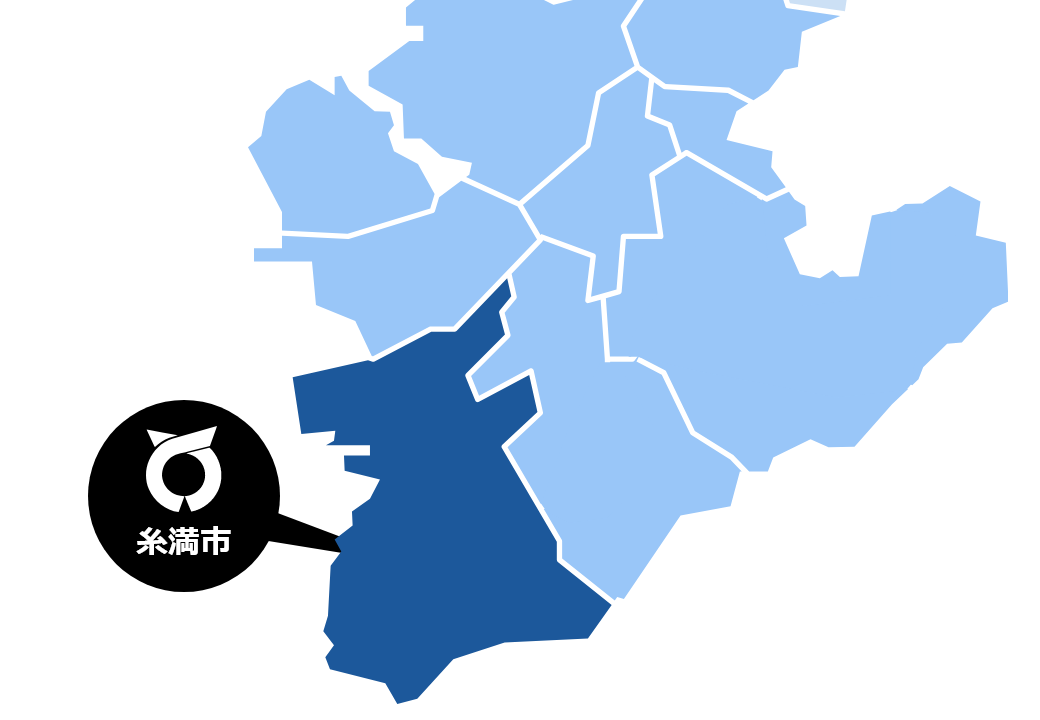本文
【保育こども園課】幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化 概要
子ども・子育て支援法が改正され、令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
【幼児教育・保育の無償化 こども家庭庁のホームページ<外部リンク>】
対象者・対象範囲
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する 3歳~5歳児クラスの子どもたち、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化になります。
新制度移行幼稚園・認定こども園・認可保育所
- 認可施設(幼稚園・保育所・こども園)を利用する3歳児クラスから小学校就学前までの児童の保育料を無償化
※認可施設(幼稚園・保育所・こども園・地域型保育事業所)を利用する0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化の対象となります。 - 幼稚園、認定こども園(1号認定)は、満3歳児(3歳になった日から最小の3月31日までにある子ども)から無償化
新制度未移行幼稚園
保育料を月額25,700円を上限として無償化
(入園料は入園初年度に限り月額換算して無償化の対象となります)
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育
- 保育の必要性があると認定を受けた、3歳児クラスから小学校就学前までの児童の月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
- 幼稚園の満3歳児については、保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯が対象。月額上限16,300円
※利用日数に応じて月額上限額の変動あり(日額上限450円×利用日数)
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター
- 保育の必要性があると認定を受けた、保育所等を利用していない3歳児クラスから小学校就学前までの児童の保育料を月額37,000円を上限に無償化
- 保育の必要性があると認定を受けた、保育所等を利用していない住民税非課税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童の保育料を月額42,000円を上限に無償化
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
●令和6年10月から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となり、保育料が全額自己負担となります。 なお、現在利用している施設または利用を予定している施設が「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設かどうかは、下記の沖縄県のホームページで確認していただくか、直接施設へお問合せください。
【沖縄県ホームページ:沖縄県内の認可外保育施設に関する情報】<外部リンク> →沖縄県ホームページに掲載されている「認可外保育施設一覧表」で指導監督基準証明書交付が「有」となっている施設は指導監督基準を満たしている施設です。
施設等利用給付(無償化)認定申請について
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、サービスを利用する前に施設等利用給付認定を申請していただく必要があります。
※ただし、認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び新制度幼稚園に在園する児童は改めての手続きは必要ありません。
新制度未移行幼稚園(預かり保育を利用しない方)
1. 申請書(預かり保育を利用しない方) [PDFファイル/179KB]
※保育を必要とする理由の要件に該当しない場合は、こちらの申請となります。
新制度未移行幼稚園、新制度幼稚園・認定こども園(教育)の預かり保育を利用される方
- 申請書(預かり保育を利用される方) [PDFファイル/3.17MB]
- 保育を必要とする理由の要件書類(「保護者の保育を必要とする証明」参照)
※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません
※満3歳児については、住民税非課税世帯または保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターを利用される方
- 申請書(認可外保育施設等を利用される方) [PDFファイル/3.17MB]
- 保育を必要とする理由の要件書類(「保護者の保育を必要とする証明」参照)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(該当する方のみ提出)[PDFファイル/313KB]
- 別世帯状況申立書(該当する方のみ提出) [PDFファイル/386KB]
※保育を必要とする理由に該当しない場合は、無償化の対象となりません
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
●令和6年10月から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となり、保育料が全額自己負担となります。 なお、現在利用している施設または利用を予定している施設が「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設かどうかは、下記の沖縄県のホームページで確認していただくか、直接施設へお問合せください。
【沖縄県ホームページ:沖縄県内の認可外保育施設に関する情報】<外部リンク> →沖縄県ホームページに掲載されている「認可外保育施設一覧表」で指導監督基準証明書交付が「有」となっている施設は指導監督基準を満たしている施設です。
提出期限・受付時間
提出期限:認定を受けたい1週間前まで
受付時間:午前9時~11時、午後1時~午後4時30分
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付場所:糸満市役所2階 糸満市保育こども園課 保育・こども園係(2階23番窓口)
保育を必要とする理由
注意点
利用申込をされる場合は、必ず次の事項をご確認の上、該当する書類を提出してください。書類不備の場合は受付ができません。あらかじめご了承ください。
きょうだいで申し込みをする際の各種書類は、原本を上のお子さまに、写しを下のお子さまにコピーを添付してください。
保育こども園課で提出書類などのコピーは行いませんのでご注意ください。市役所1階にあるコピー機(有料)をご利用ください。
「◆」の印がついている書類は、必ず糸満市の様式でご提出ください。
保護者の保育を必要とする証明
預かり保育を利用しない未移行(旧制度)幼稚園は必要ありません。
預かり保育を利用する未移行(旧制度)幼稚園は必要となります。
無償化対象は、保護者(父母とも)が仕事または病気等のため保育する方がいない児童となります。
| 保育を必要とする理由 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 就労の人 |
雇用されている方 (会社員・公務員・パート・派遣・単身赴任) |
※育児休業からの復帰を希望する場合は、復帰日の記載が必要です。 |
| 自営業(協力者含む)、委託、内職等の場合 | ||
| 妊娠・出産の人 |
|
|
| 保護者の疾病・障害の人 |
診断書(保護者の疾病理由用) [PDFファイル/53KB] ◆ お持ちの方は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」などの写し |
|
| 親族の介護・看護の人 | ||
| 災害復旧の人 |
罹災証明書等の被災を確認できる書類 |
|
| 求職(起業準備中)の人 | ||
| 就学の人 |
|
|
| 育児休業の人 |
もしくは どちらも育休期間記載があること。 |
|
該当する方のみ必要な書類
| 保育を必要とする理由 | 必要書類 |
|---|---|
|
母子・父子世帯 |
戸籍謄本等(受理証明書も可)、児童扶養手当受給者証の写し、母子及び父子家庭医療費受給者証の写しのいずれか |
|
同住所に別世帯がある人 (0~2歳児クラスが対象です) |
※電気、水道、ガス料金のいずれかの領収書(双方)直近のものを添付 |
| 教育・保育施設への申込が不実施で認可外保育施設を利用しているまたは利用を予定される方 | 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル/72KB] |
「◆」の印がついている書類は、必ず糸満市の様式でご提出ください。
そのほか、必要に応じて書類を追加提出していただくことがあります。
ご提出の前に
提出書類はすべて揃っていますか?保育施設等利用申込チェックシートでご確認ください。
特定子ども・子育て支援施設等の確認及び糸満市内の対象施設について(令和6年4月8日現在)
下記施設については、子ども・子育て支援施設として確認しました(糸満市内の無償化対象施設)
施設等利用給付(無償化)の給付方法について
給付方法
施設等利用給付費の給付方法については、施設によって償還払いまたは現物給付(法定代理受領)及びその両方の方法により給付します。
- 償還払い・・・いったん保護者が費用を支払い、必要書類提出後、市から払い戻しを受ける
- 現物給付(法定代理受領)・・・市が保護者に代わって施設に費用を支払う
請求書類(償還払い)※保護者請求
1.請求書(保護者作成)
2.領収書兼提供証明書(施設作成)
領収書兼提供証明書(2・3号)[Excelファイル/16KB]
請求書類(現物給付)※施設請求
1.請求書(施設作成)
請求書(新制度未移行幼稚園)[Excelファイル/44KB]
2.提供証明書(施設作成)