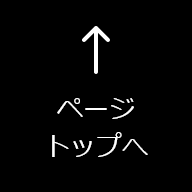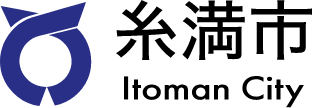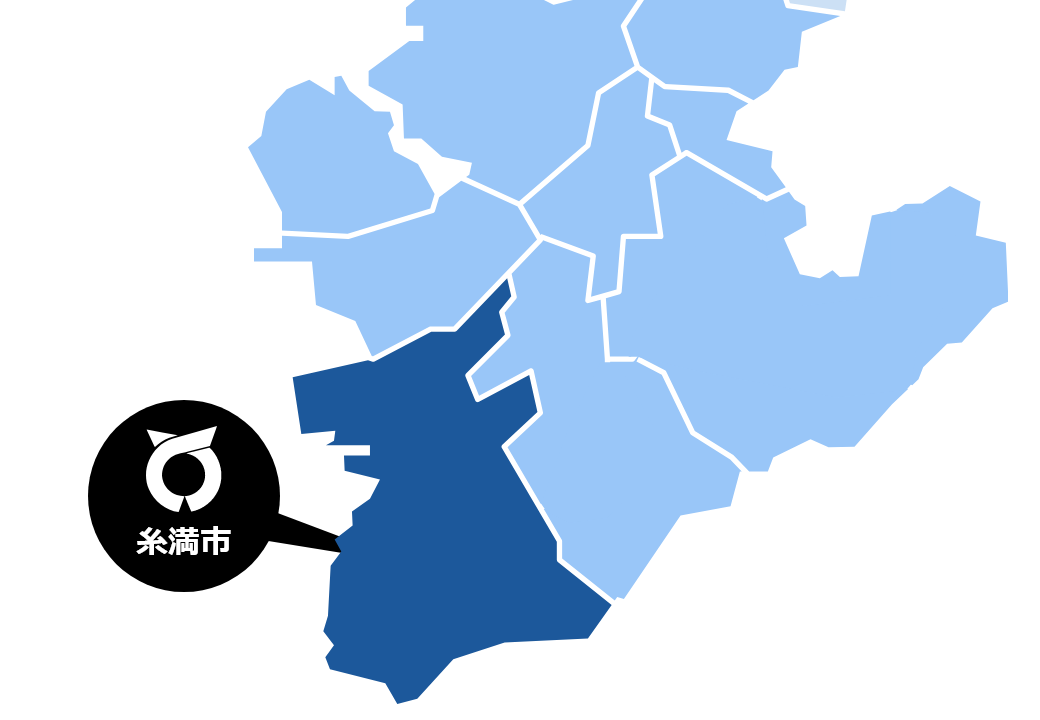本文
市史だより146 (「広報いとまん」 平成17年8月号)徳之島のイチマンチュ
この写真は、字糸満の大城秀次さん所有の一枚です。昭和十年代の中頃から後半にかけて、徳之島の天城村(現天城町)浅間の湾屋という集落で撮影したもので、徳之島で追込網漁業をしていた糸満出身の漁民とその家族、雇子(ヤトゥイングヮ)たちが写っています。男性の何人かはウェーク(櫂)を、女性たちはカミアキネー(頭上に商品を載せて行商すること)に使うバーキ(竹かご)と竿ばかりを手にしています。人々は皆裸足で、当時の質素な暮らしぶりが感じられます。
後列右から60人目の男性が大城さんです。当時、大城さんが住んでいた徳之島の東天城村の山(さん)という土地には、「前仲大殿内」(メーナカウードゥンチ)など追込網をするために糸満から移り住んだウミンチューの家庭がいくつかあり、それぞれが数人の雇子を抱えていました。ムロアジやグルクンなどの漁では、彼らウミンチューは南方(ヘーカタ)と北方(ニシカタ)と呼ばれる二つの組に分かれて、別々の場所で操業していました。ところがこの頃になると、満期になった雇子が長崎県五島の網組に入ったり、若い男性が次々と兵隊にとられたりと、島の漁業者が少なくなり、南方と北方は合同で追い込み漁をするようになりました。撮影地の湾屋は元々北方の漁場でしたが、南方に属していた大城さんたちも、このような事情から湾屋方面で漁をしました。写真撮影の当日は、海が時化(しけ)て漁に出られず、大勢の人々が集まって写真を撮ることになった、と大城さんは話します。
大城さんの家では、明治の末ごろ父の喜三郎さんが兄弟で追込網をするために、徳之島の山に移り住むようになりました。大城さん自身は大正12年に山で生まれ幼少期を過ごし、糸満で学校を卒業した後、徳之島に戻り漁業をしました。
終戦後、父親が先に糸満に戻り、昭和26年ごろ大城さん自身も妻子とともに、徳之島から糸満に引き揚げました。島を引き揚げて五十数年が経ちますが、大城さんは「徳之島も糸満も大切な故郷」と語ります。
※カタカナで振り仮名をつけているのは方言読みです。

市史だよりNo. 130/132/133/134/135/136/137/138/139/140
141/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152