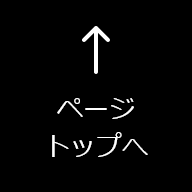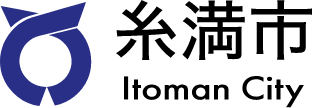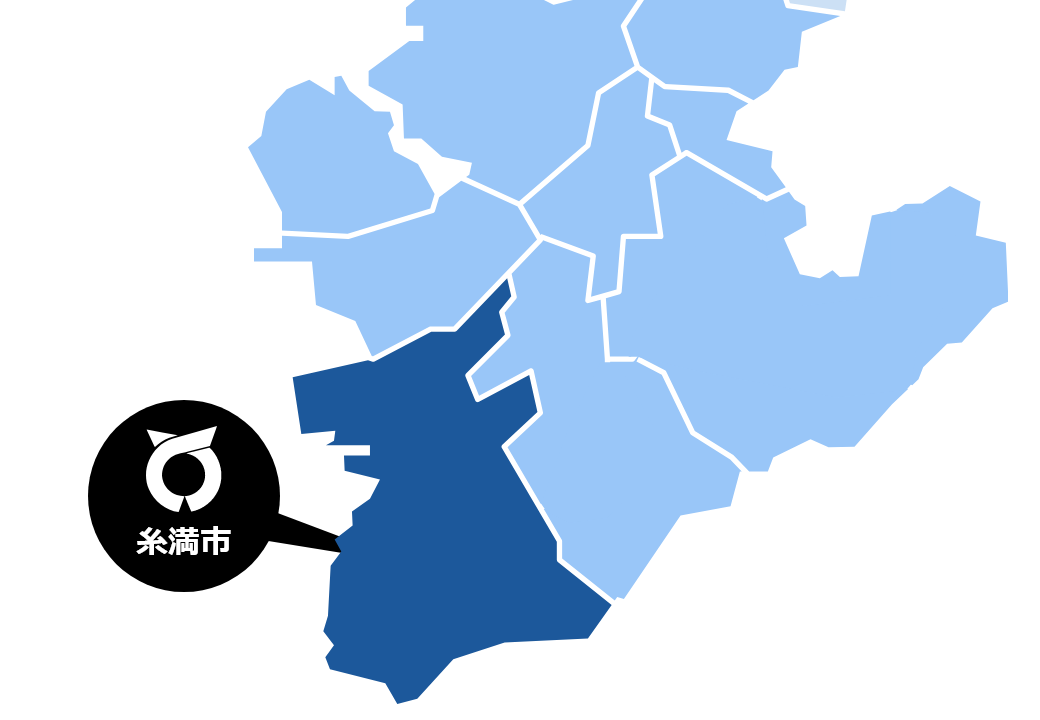本文
市史だより151 (「広報いとまん」 平成19年9月号) 写真展「甦る記憶」より

先月、市役所で開催された写真展「甦る記憶 東風平朝正が撮ったいとまん」は、市内外から連日大勢の方々にお越しいただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。会場では年配の方々には懐かしさを、若い方々には新鮮な驚きをもって、写真展をご覧いただいたようです。今回は、その写真展のなかから、1957、8年ごろ糸満漁港の西側埋め立て地に建設された、鯨体処理場(クジラ工場)での作業風景の写真をご紹介します。
鯨体処理場とは、沖縄近海で捕獲されたクジラの完全利用化を目的に設置された、クジラの解体処理施設のことです。県内には糸満のほかに、名護、佐敷に同様の施設がありました。沖縄近海での捕鯨は1950年代後半より本格的に行われるようになり、これまで年間捕獲頭数が20頭前後であったのに対し、1958年には290頭、59年には224頭を記録しています。これは捕鯨船の隻数が増加したことによるものですが、乱獲が資源の枯渇を招き、60年182頭、61年99頭、62年24頭と、捕獲数が激減していきます。これにより、捕鯨そのものが中止に追い込まれ、鯨体処理場での作業も見ることができなくなりました。
東風平朝正さん撮影によるこの一コマは、陸揚げされたクジラを、柄の長い刀で切れ目を入れながら、肉塊・皮脂肪などに解体していく様子をとらえたものです。
1962年に、糸満の鯨体処理場「大洋漁業株式会社」の事務員をしていた字糸満の玉城勝子さんは「処理場では本土から来た大勢の技術者が働いていて、敷地内には職員のための食堂もあった。もう、このころになると、捕獲されるクジラは少なくなっていた。クジラは陸揚げされると、ウィンチで巻き上げて皮脂肪をはいでいった」と話していました。また、会場を訪れた方々からは「クジラが揚がってくると、走って見に行った」「風向きによっては、潮平辺りまでクジラの臭いがした」「ウバと呼んでいた脂身が、コリコリとした歯ごたえで美味しかった」と当時を懐かしむ声が聞かれました。
市史だよりNo. 130/132/133/134/135/136/137/138/139/140
141/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152